各ツールの名称
ペン
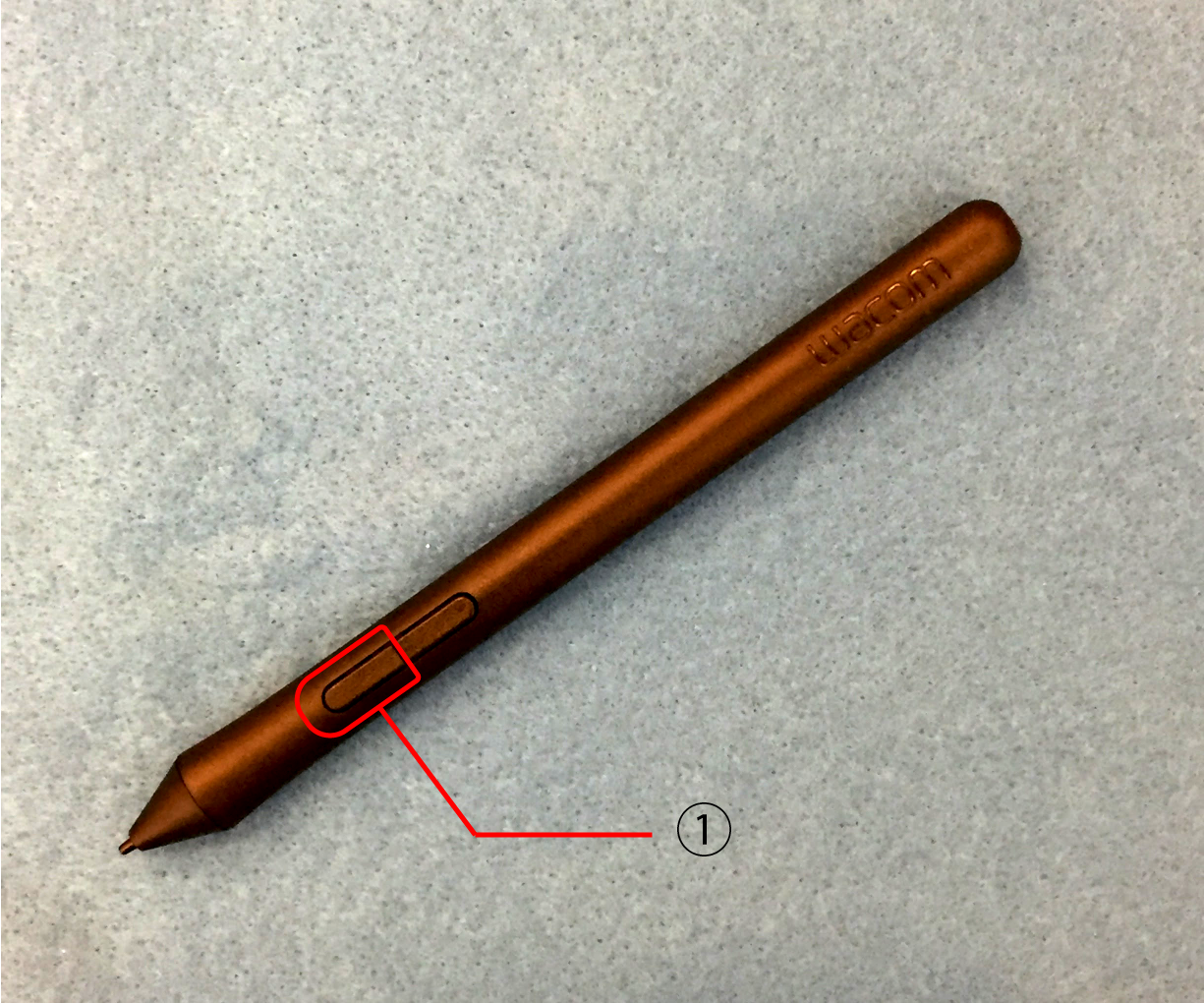
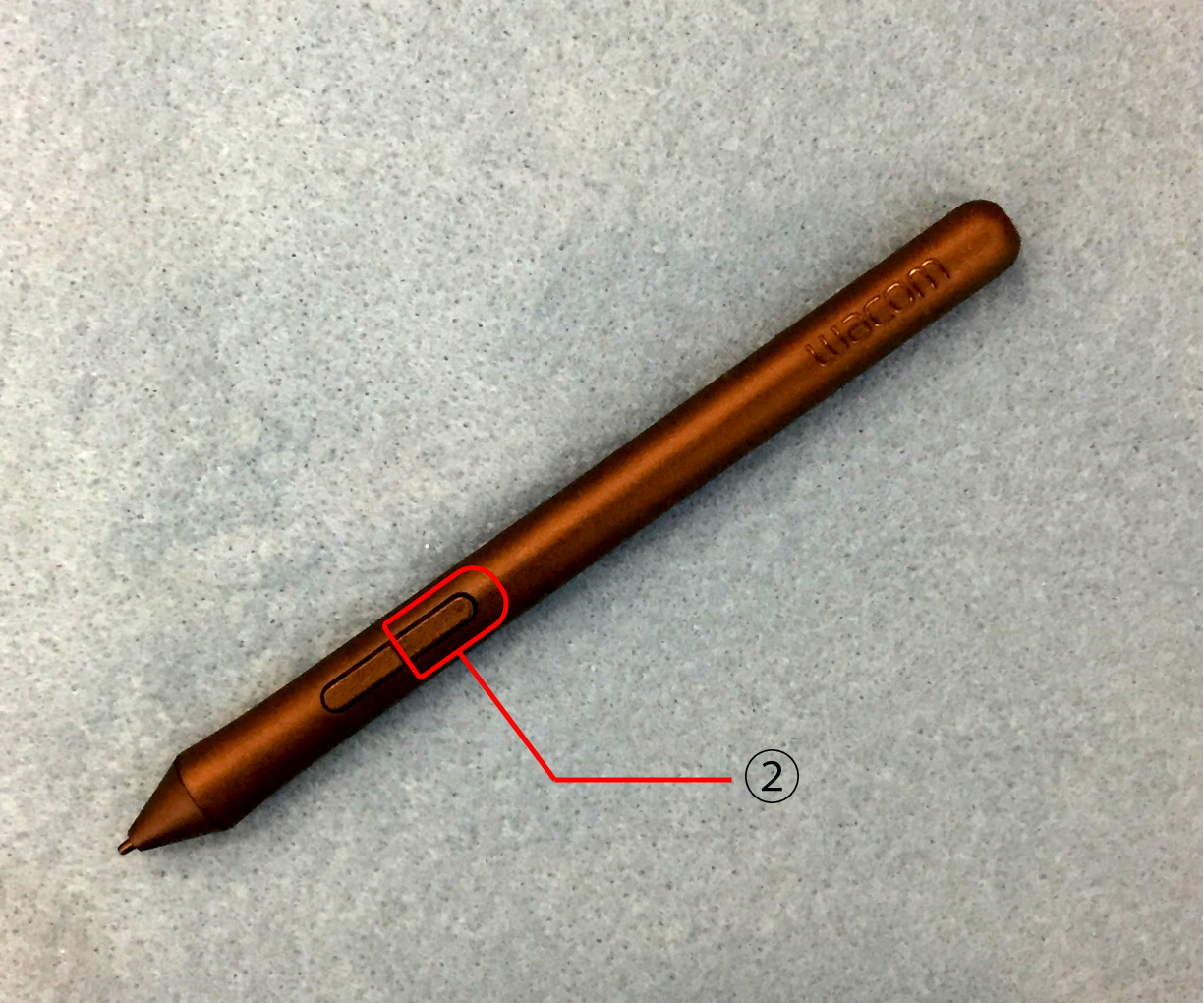
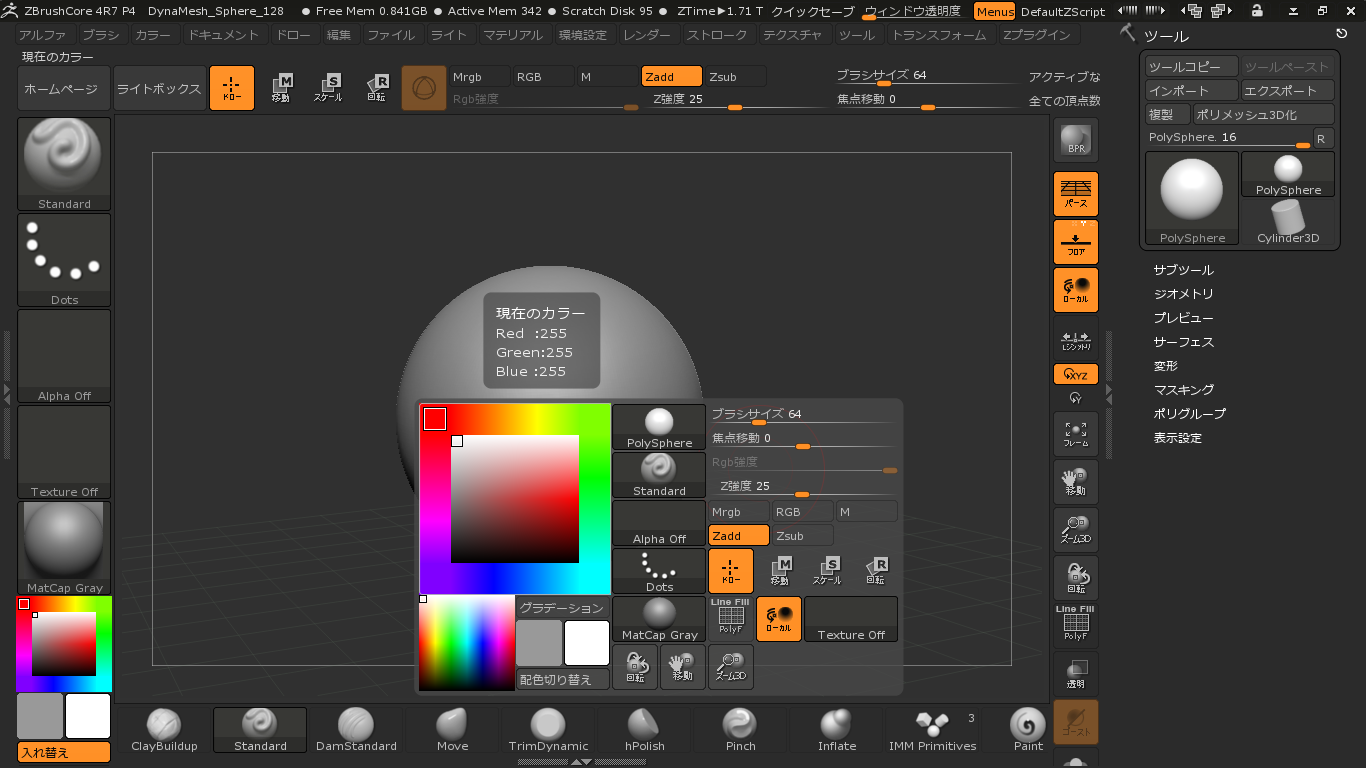
基本操作
「クリック」:ペン先でタブレットをタッチ
※筆圧で、ペンの効果(太さ、効果)も変化する
「カーソルを動かす」:ペンをタブレットから浮かせた状態で動かす
※タブレットに触れてしまうと、オブジェクトの向きが変わってしまう
ボタン説明
写真「①」:ブラシ「Smooth」機能
※ブラシの効果が滑らかになる
写真「②」:クイックメニュー
※ブラシの太さ、種類等を変更できる
タブレット
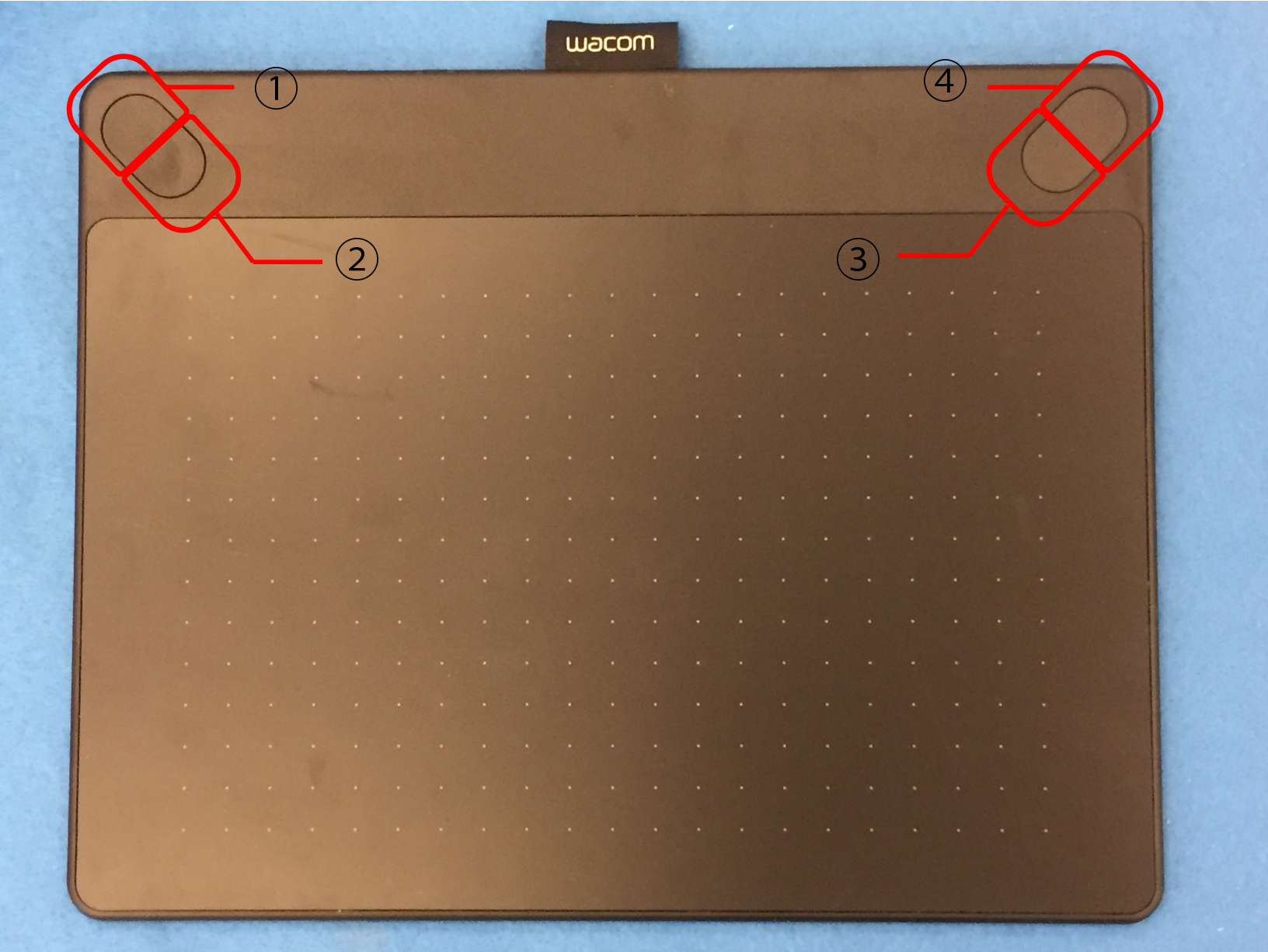
タブレットのボタン説明
写真「②」:alt
写真「③」:クイックメニュー
※ペンの太さ、種類変更などのメニュー
写真「④」:ブラシパレット
※ブラシを選択するメニュー
画面
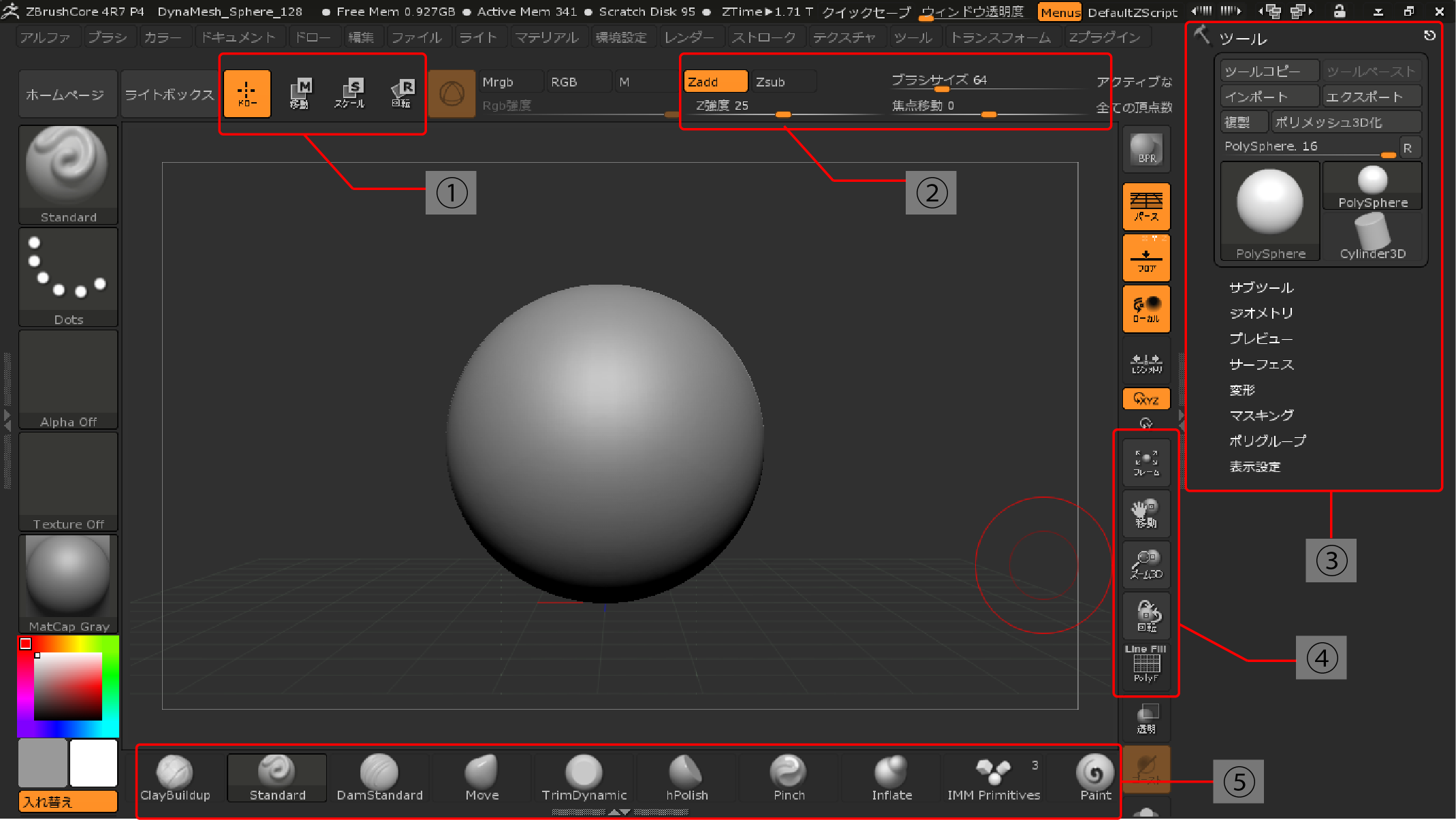
画面操作
写真「①」:3Dモデルに加工を加える
※「ドロー」で3Dモデルの一部分に加工を加える
※「移動」で3Dモデルのコピー、大きさ・長さの変更
写真「②」:ブラシの太さを変える
※「ブラシサイズ」:太さ
※「Z強度」:ブラシ効果を強くする
※「焦点移動」:ブラシ効果の角を急斜面にする
写真「③」:ツールを選択する
写真「④」:シーン(作業するための空間)の変更
写真「⑤」:ブラシの変更
キー操作
キーボードのキーまたは、タブレットのボタン操作
「X」

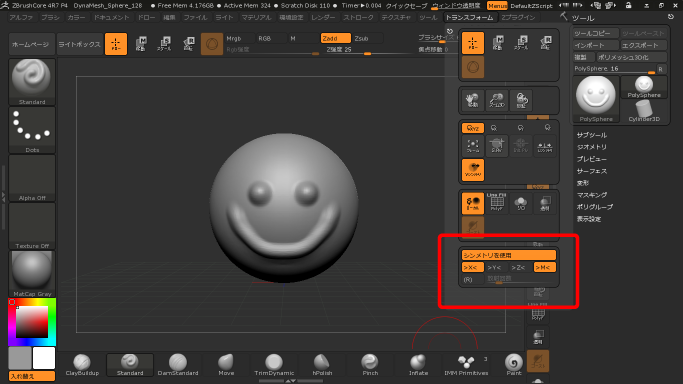
「X」:左右対称を設定/解除
ZBrushCoreの初期設定では、左右対称になっている
写真のような左右対称の造形をする際には便利!
そうでないときには「X」で解除する
※「トランスフォーム」の「シンメトリを使用」からでも設定/解除は可能
「>X<」:X軸に対して左右対称
「Ctrl」


「Ctrl」+「Z」:元に戻る
「Ctrl」を押しながら移動(写真「②」):複製
※「ドロー」から「移動」に切り替える(写真「①」)
「Ctrl」+「alt」を押しながら移動:複製したものでくり抜く
※「ドロー」から「移動」に切り替える
手順(写真2参照)
1)写真「A」:「Ctrl」+「alt」を押しながら3Dモデルを移動させる
2)写真「B」:「Ctrl」→
「Ctrl」+シーンをドラッグ(マスクの解除)→
「Ctrl」+シーンをドラッグ(面の貼り直し)
3)写真「C」、「D」:複製したものでくり抜いた結果
「Ctrl」を押しながらオブジェクトをタッチ:マスク
「Ctrl」を押しながらシーンをタッチ:マスク内選択
「shift」
「shift」を押しながら3Dモデルをクリック:ブラシ「Smooth」機能
「shift」+「F」:メッシュで表示
※でこぼこしていた造形が滑らかになる
「shift」を押しながらシーン(作業するための空間)をクリック:3Dモデルの向きを正面にする
「shift」+「F」:メッシュで表示
「alt」
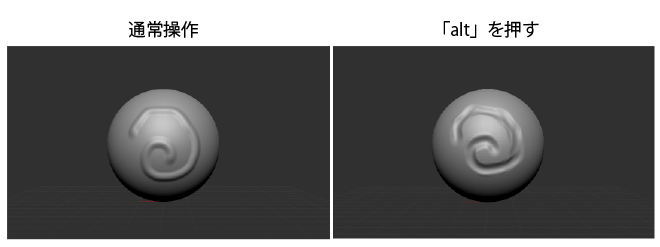
「alt」を押しながら3Dモデルをクリック:ブラシ効果が逆になる
「alt」を押しながらシーン(作業するための空間)をクリック:移動
※向きを変えずに3Dモデルを移動できる
「s」
「s」キーを押しながらドラッグ:ブラシサイズの変更
操作説明
ライトボックス
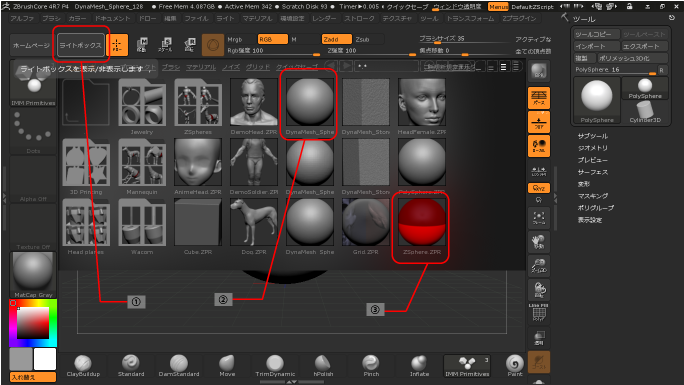

ZBrushCoreを起動すると、この画面が表示される
3Dモデルはゼロからのスタートでなく、ある程度の形から造形をはじめられる
通常は写真「②」の丸を選択
※下の丸はダイナメッシュが荒い
自由に造形がしたい場合は写真「③」を選択
※写真2のように、自由に形を追加でき、また大きさ、長さの変更が容易
選択後に形を選びなおしたい、新規作成したい場合は写真「①」をクリック
その他の形からスタートする
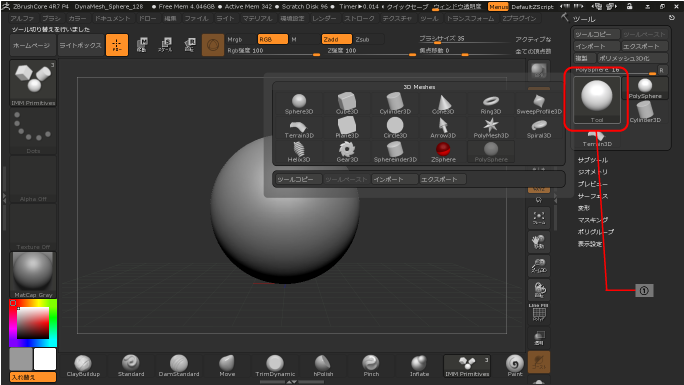
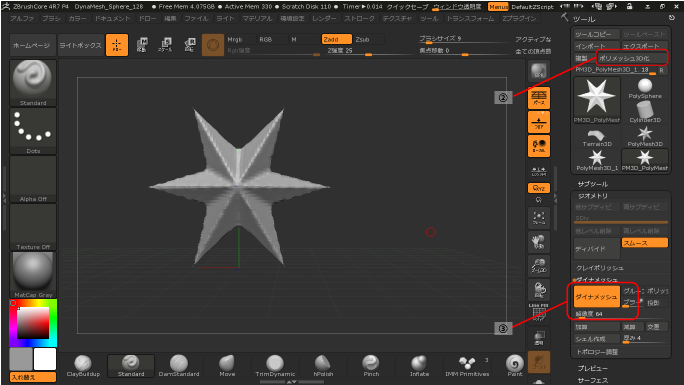
ライトボックス以外からもスタートの形が選択できる
写真「①」を長押しすると、いろいろな形が出現する
※このままでは造形ができない!
手順
1)写真「②」の「ポリメッシュ3D化」をクリック
2)写真「③」の解像度を下げ「ダイナメッシュ」をクリック
※解像度はが高すぎると、メッシュの数が多くなりデータが壊れてしまうことがる
ブラシ
ブラシごとで効果が異なる
よく使うブラシは
「Standard」:線を描いたり、部分的に太くする
「Move」:ひきのばす
「IMMPrimitives」:形を加える
※「IMMPrimitives」をクリック後「M」を押すと加える形が選択できる
ギズモ3D
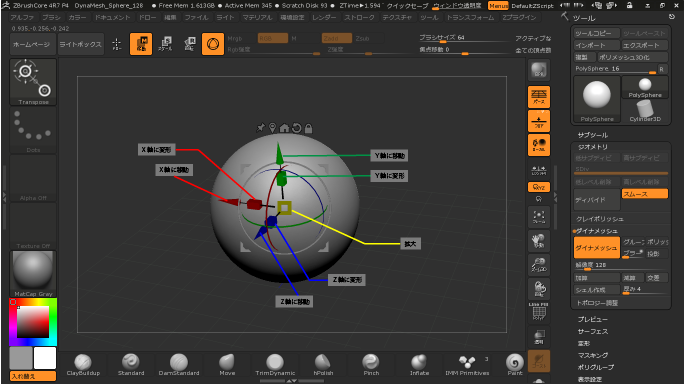
赤・青・緑の三角形:移動
赤・青・緑の四角形:変形
黄色:拡大・縮小
※「ドロー」から「移動」に切り替える
やってみた結果
実際にやってみた結果
やってみた1号

データ
・同じ形でくり抜いた
・お皿のような形
・解像度は初期のまま「128」
結果
・サイズ設定ができないため3Dプリンター設定の際にサイズを入力
・メッシュ数が多い/画像サイズ4,228KBで、データが壊れたためプリントできず
・別アプリを使ってメッシュの数を少なくしてプリントできた
やってみた2号
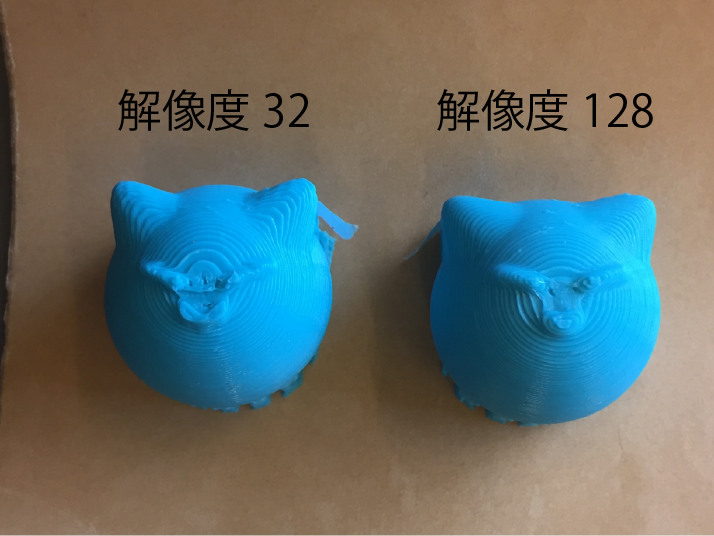
データ
・ブラシ「standard」、「move」を使ってデータ作成
・解像度を「128」と「32」でそれぞれデータを作成
結果
・どちらの解像度でもデータが壊れなかった
→へこますとデータが壊れやすい?【やってみた1号の結果より】
・解像度が荒い分、層と層の間が広くなる
モデリングのコツ
ここではZBrushCoreを使う上で重要となってくる細かいテクニックを紹介します。
「Move」で大まかな形を形成
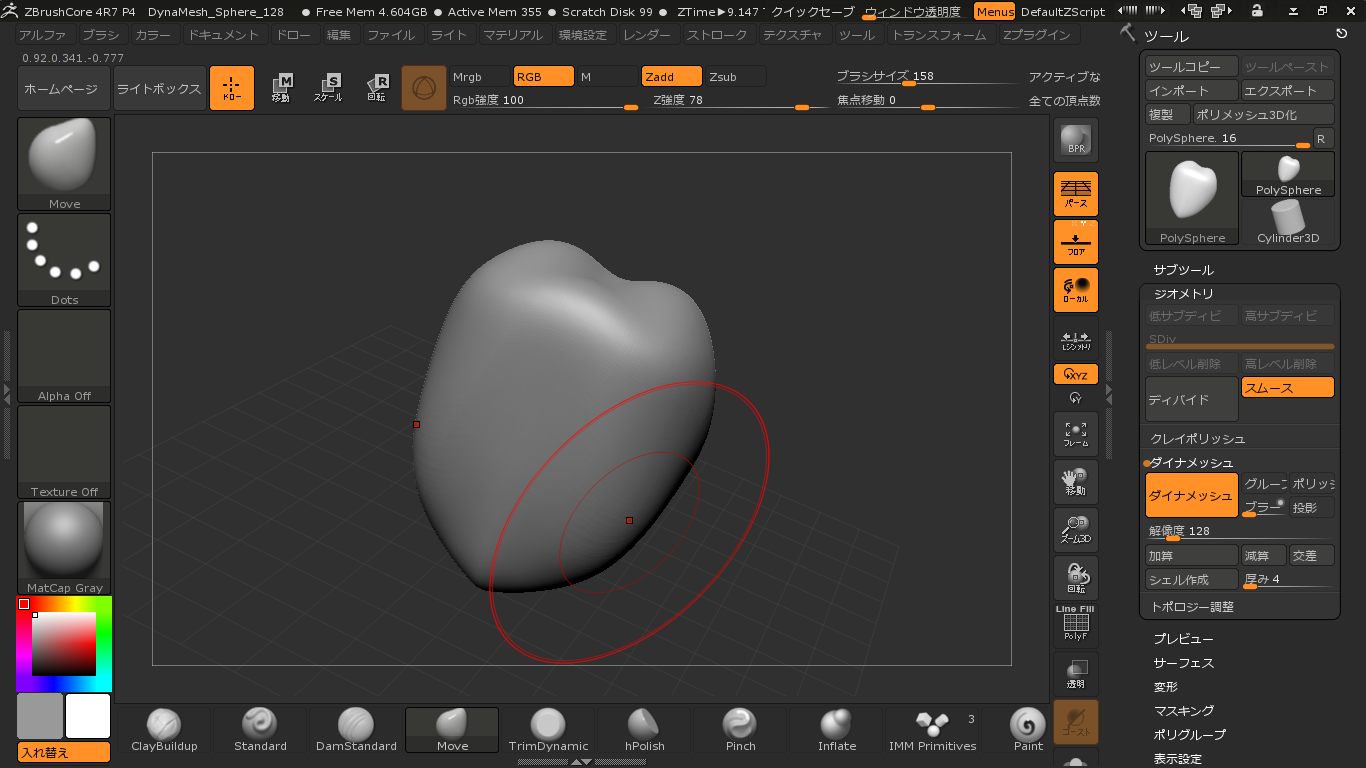
ブラシは「Move」を選びます。
ブラシのサイズを大きくし、Z強度をあげます。
粘土をこねるように押したり引いたりして、球体を大まかに作りたい形にもっていきます。
「ダイナメッシュ」を使いこなす
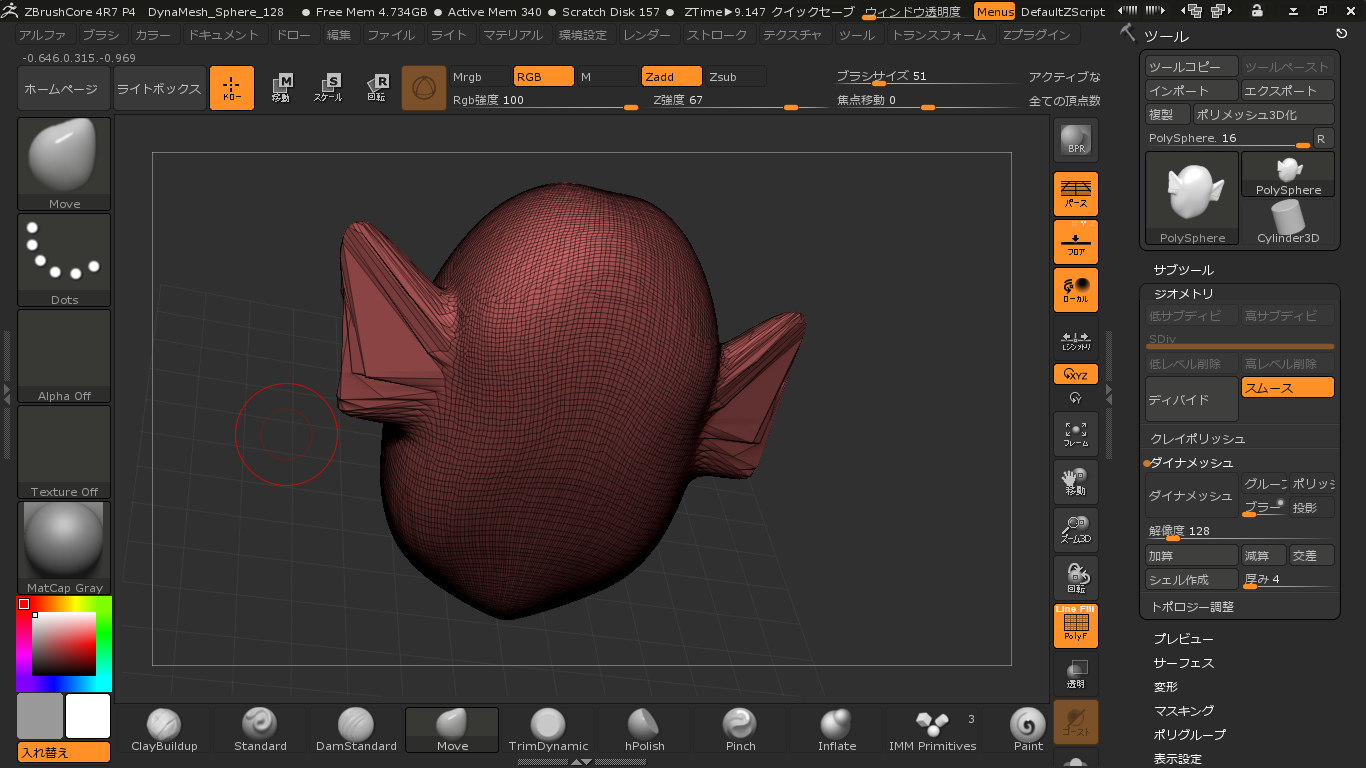
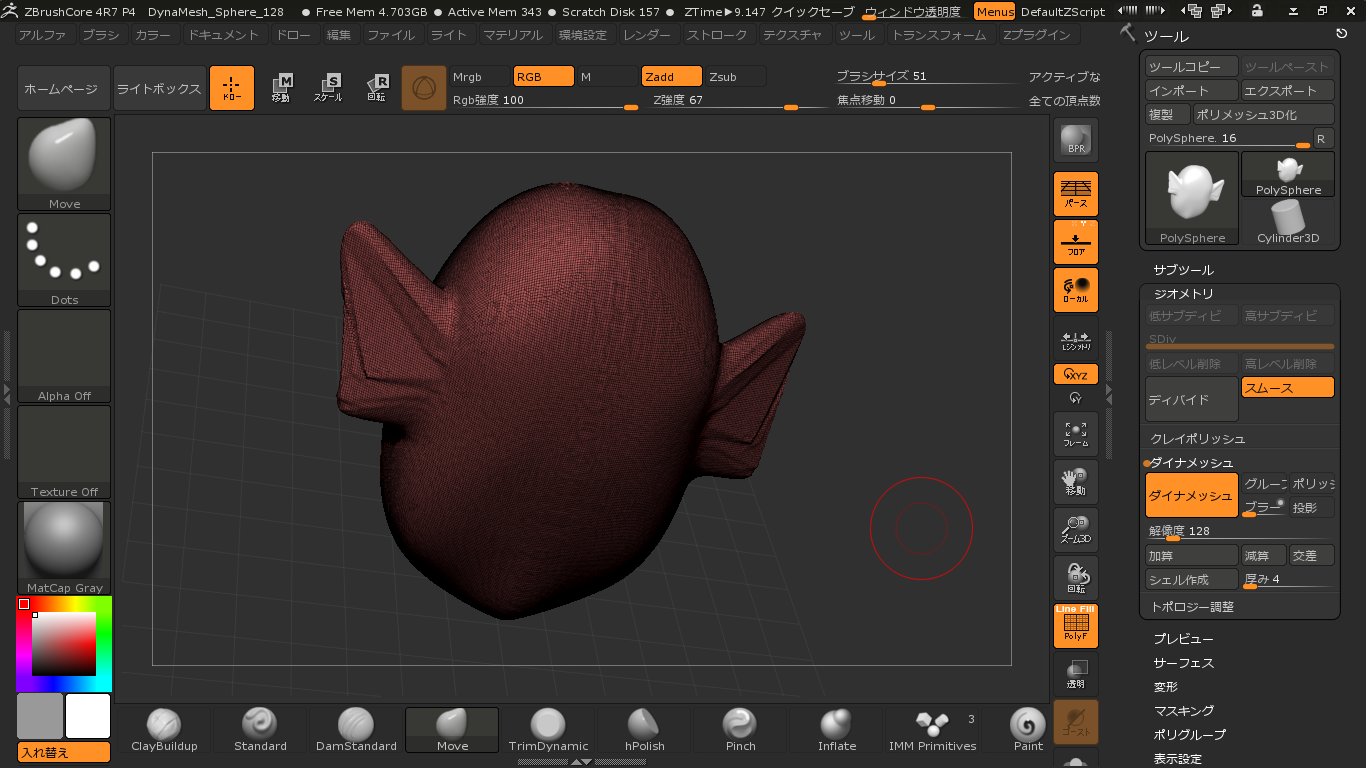
右のツールメニューの中にある「ジオメトリ」をクリックします。
その中にある「ダイナメッシュ」というボタンを使います。
「Shift」+「F」キーでモデルをメッシュ状態で見ることができます。
図1では耳の部分のメッシュが粗いことが確認できます。
ここで「ダイナメッシュ」ボタンを押すと、この形状の上から再びメッシュを貼り直してくれます。これにより、モデルがギザギザにならず、滑らかに変形できるようになります。
「Shift」を押しながらモデルをなぞり、スムーズにしていきましょう。
「マスク」を使いこなす

「Ctrl」を押しながらモデルをなぞると、マスクを貼ることができます。
変形をしたい部分にマスクを貼りましょう。
マスクで目と口の部分をくり抜きたいと思います。
「マスク」を反転
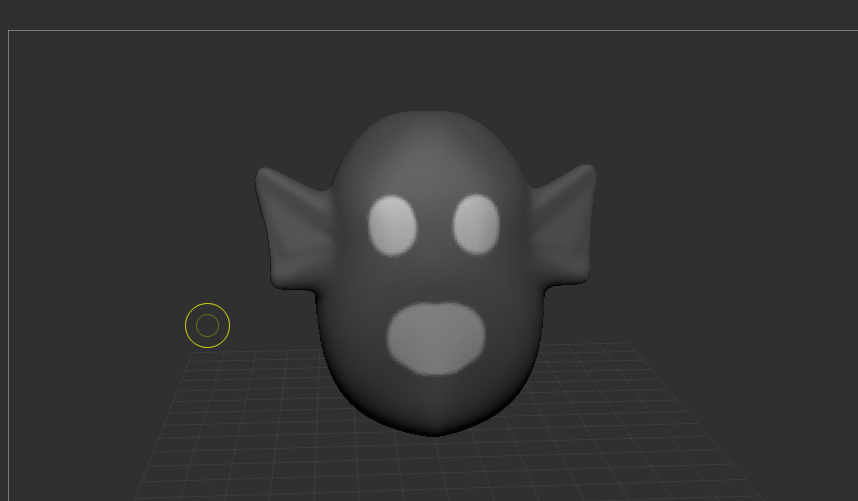
マスクを貼りたい範囲が決まったら、「Ctrl」を押しながらモデル以外のところをタッチしましょう。
マスクが反転し、選択している部分以外が黒くなります。
この状態では、白い部分のみ変形が可能になります。
「マスク」を貼った部分を変形する
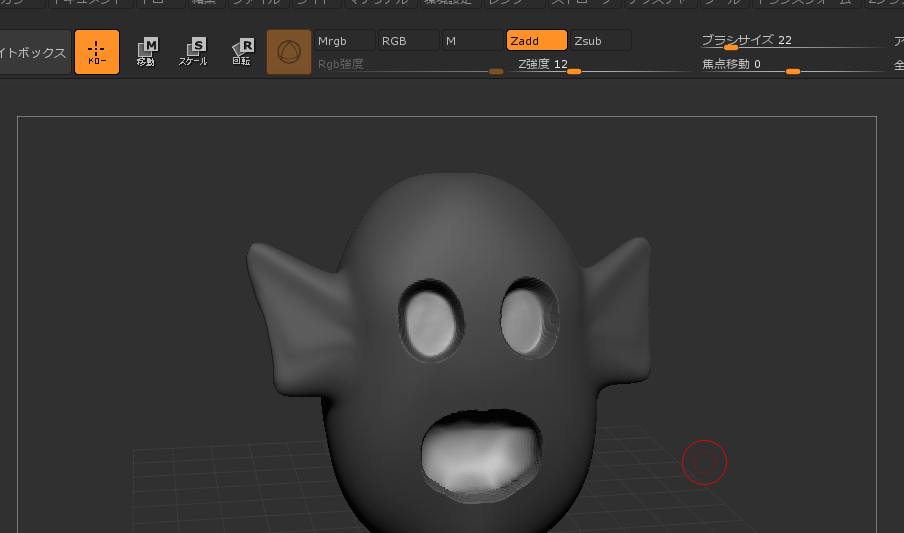
目と口の部分をくり抜きたいため、ブラシは「Standard」を選び、Z強度を上げ「Alt」を押しながら白い部分をなぞりましょう。
白い部分のみがへこみます。
マスクの解除は、「Ctrl」を押しながら、モデル上ではないところをドラッグをします。
「Move」で細かい変形
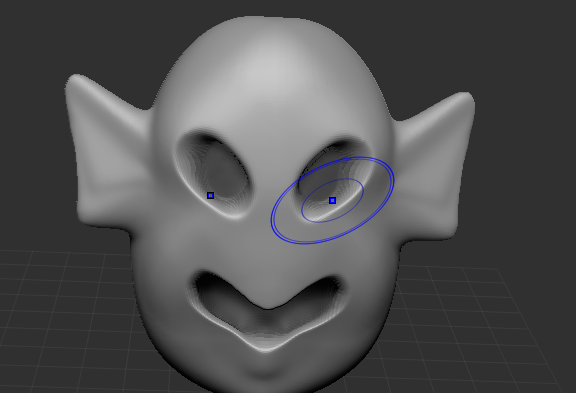
細かな変形をしたい場合はブラシで「Move」を選択し、ブラシサイズとZ強度を変更しながら、形を調整していきます。
「Move」後にはこまめにスムーズさせるといいでしょう。
より細かい変形
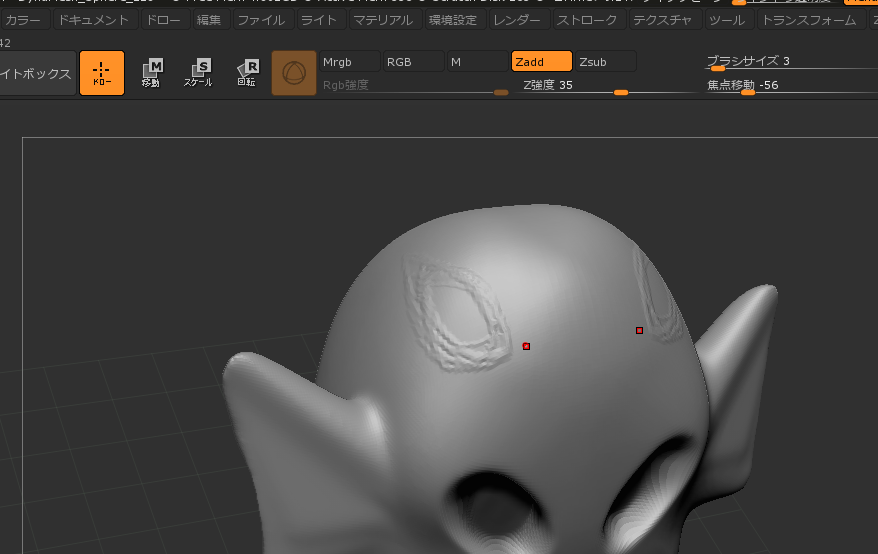
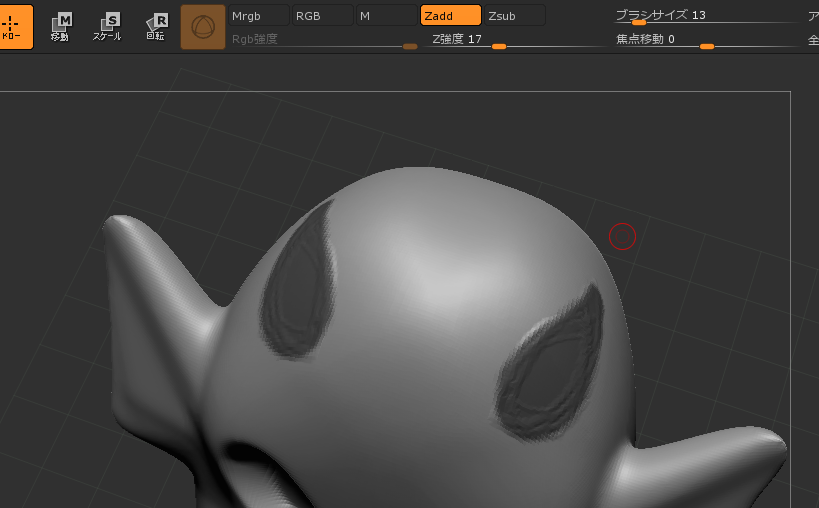
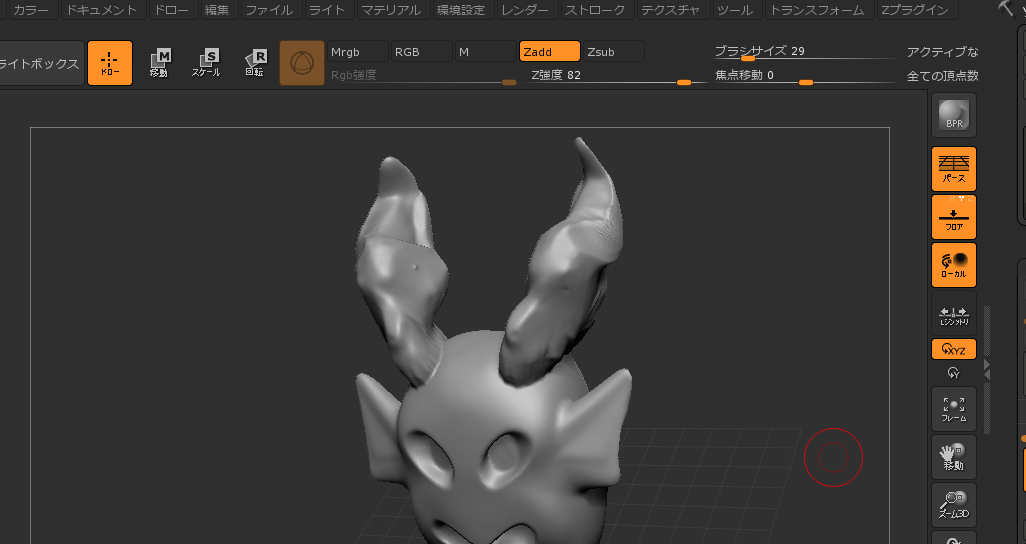
繊細な変形が必要であったり、モデル上に下書きをしてみたい時は、「Standard」でブラシサイズを小さく、Z強度を強めに取りましょう。
鉛筆で下書きをするようにモデルに書き込むことができます。
図ではモデルに角をつける位置を下書きし、そこにマスクを塗り、角を生やしました。
こういった様々なツールを駆使し、モデルの造形を少しずつ形成していきます。