2024年6~8月 JICA海外協力隊・理学療法士隊員(以下、『隊員』)が配属先の高齢者施設にて障害を持つ入居者の機能・能力に応じた自助具が不足していることを課題であると認識した。入居者は皆、経済的自立困難であり、身寄りが無いという背景もあり自身で購入することができない。その後、隊員が現地理学療法士(以下、『現地PT』)に共に自助具を作成することを提案しプロジェクトが始動した。
- 全体像:
70歳代男性。パーキンソン病を患っており、ベッド、または車椅子で生活している。1日の中で5時間ほど車椅子に乗車して入浴、トイレ、イスラム教のイベントの参加などを行っている。
課題発見に繋がる背景:
各生活動作の中で車いすブレーキをせずに動作を行う様子が散見された。ベッド‐車椅子間の移乗、立ち上がり、トイレ⁻車椅子間の移乗が主に課題が見られる状況である。 - 要因:
1.パーキンソン病による筋力低下とバラン能力低下、安静時振戦。
2.車椅子の既存ブレーキレバーの長さが短く、ブレーキ操作時に強いトルクを必要とする。健常者なら可能だが、筋力低下がある者では労作を強いることになる。
3.車椅子の既存ブレーキレバーの形が小さく高齢者には目視や触知で見つけづらい。 これらの要因により対象者は入居生活の中で不便を感じていながらも生活のため致し方なくブレーキをかけずに動作を行っていた。
.jpg)
.22.26_88a0ff1e.jpg)

.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.MP.jpg)
.MP.jpg)
.jpg)
.jpg)
.MP.jpg)
.MP.jpg)
.jpg)
.jpg)
.22.18_14364bca.jpg)
.22.26_88a0ff1e.jpg)
.22.18_14364bca.jpg)
.22.26_88a0ff1e.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
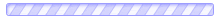
Comments